

 頸髄損傷になった当時を思い出す
頸髄損傷になった当時を思い出す 
2006年7月21日、階段での転落事故で意識不明になり、市内の脳神経外科の病院に救急搬送された。翌朝、妻の声で目が覚めた。「階段から落ちて、救急車で運ばれて、今まで昏睡状態だったんだよ!」と妻から説明されて、自分が病院のベッドにいることがわかった。間もなく、幼少期に体験した“かなしばり”に似た感覚を味わうことになった。はじめのうちは、まだ寝ぼけているせいなんだろうと思ったが、数分たっても手足の感覚は戻らなかった。家族が、手や足をさすったりするが、どこを触られているのかがわからなかった。急に恐怖感におそわれていき、頭が混乱していった。
その日、駆けつけてくれた勤務先の上司へ進行中の案件を説明して仕事を託した。
翌日から5日間、高濃度酸素カプセルに1時間入れられた。閉所恐怖症の私にとって地獄の体験だった。
数日後、集中治療室から一般病棟へ移った。ある朝、回診の医師の後を金魚のフンみたいについて歩く研修医の若僧から、「戸羽さんは神経がズタズタになってるから、かなりリハビリ頑張らないとダメみたいだよ。」と言われた。この言葉を聞いて、リハビリをこなせば治るんだろうと安易に考えていた。
入院してから3週間ほど経過して、脳神経外科の主治医から病状説明を受けることになった。「脊椎動物は大小を問わず、キリンのように首が長くても、首の骨は7個なんです」という説明から始まったのをよく覚えている。MRI画像を見ながら、上から4つめの頸椎の付近で白く見えるところの脊髄がつぶれており、これから一生、歩くことはできないし、肩から下は動かすことができないであろうと宣告された。唖然(あぜん)としたが、不思議なことに、動揺することなく聞いていた。四肢マヒで生きていくことの現実がまったくわかっていなかったためだと思う。
一人っ子の当時5歳だった娘にとって、私は体力系の遊び相手の第一人者であったが、もう一緒に遊んでやれないと思うと、切なくなった。3人家族にとって一番の趣味だったキャンプにも行けなくなった。転落事故の数日前にSnow Peak製の高価なキャンプ用品を買ったばかりであり、とても悔しい思いをした。一度も使わないままお蔵入りとなってしまった。
急性期・回復期の入院中、妻は用事のある日以外は幼い娘を連れて面会に来てくれた。それまで入院の経験が一度もなく、自力でまったく動けない私にとって、妻と娘の顔を見るのが何よりの楽しみだった。
回復期の病院には「リハビリテーション科」があった。ウェブサイトでは入院を受け入れる対象者として脊髄損傷を1番に掲げていたが、収容人数約40人のうち脊髄損傷は私1人だった。PTやOTが大勢いた。先輩格っぽいヤツらが暇そうにしてバランスボールで遊んでいたのを覚えている。その病院では、リハビリ施術中に少しでも痛そうな顔をすると、それ以上に強いストレッチをしてくれなかった。おかげで6ヶ月間で肩の可動域は90度未満になってしまった。
受傷から8ヶ月後、回復期の病院側からの最長入院期間は法定6ヶ月間という説明に従って退院した。
退院後、札幌市内の身体障害者施設へ入所した。その施設には、脳梗塞や脳性マヒ、パーキンソン病の患者が多かった。脊髄損傷患者も数人いた。1部屋3人の相部屋だった。ベッド上での排便時の臭いや、テレビや音楽、冷蔵庫のドア開閉の音など、お互いに迷惑をかけ合うが、半年もすると慣れた。この施設でのリハビリが一番キツかった! 回復期の病院での怠慢なリハビリのせいで狭められた肩の可動域を90度に広げてくれた。全国のPT名簿連番が1ケタのPTだった。リハビリ中の痛みに耐える間、自然に涙が出てきた。このPTのリハビリのおかげで、電動車椅子をジョイスティックで操縦したり、スローペースではあるがトラックボールでパソコン操作ができるようになった。彼にはとても感謝している。
回復期の病院で担当OTからスプリング式バランサーを使って自力で食べ物を口へ運ぶ練習を提案され、退院時まで練習を続けていたが、この施設には練習用のバランサーがなかった。受傷後初の電動車椅子をオーダーするときに、車椅子に装着できるバランサーを購入し、2年間その練習を続けたが、断念した。そもそも、バランサーという補助具が弱い筋力を補強する目的で使うものでないということを、あとで知った。
近年では当たり前になっているWiーFiは当時なかったので、自費でインターネット回線を敷設した。パソコンで「脊髄損傷」や「頚髄損傷」のキーワードでネット検索して「日本せきずい基金」のサイトを見つけることができた。このサイトでは脊髄損傷に関するノウハウの資料が大量に無償で提供されていた。こちらからダウンロードした資料で脊髄損傷患者にとって必要な基本的な知識を学ばせていただいた。とても感謝している。脊髄損傷再生医療が慢性期患者まで対象になる日が来たときは、是非とも大濱理事長にその第1号で治療を受けられることを願っている。
最初の身体障害者施設へ入所してから3年後に現在の全室個室の施設へ移転した。そのころの私は自宅に戻って生活することを希望していたが、2年後には、施設生活を継続することに決めた。自宅は施設から車で20分ほどの距離にある。妻と娘、妻の両親の4人で暮らしていた。父はリウマチを患っていて、痛みを抑えるためにステロイド薬を服用していた。6年前にすい炎を発症したが、ステロイド過剰摂取のため、すい臓の8割が自分のすい液で溶けても痛みを感じることができず、自覚症状がなかったのだ。体調不良を訴え、短期間の入院後に死亡した。肋骨が何本か折れていたと聞いた。ステロイドが恐ろしいものだと知った。母は9年前に脳梗塞で左半身に軽いマヒを負った。今年5月に脳梗塞を再発してマヒが重たくなった。このような家庭に私が戻るとどうなるか? これを考えると答えは明らかだった。妻の負担を増やして心身ともに疲れさせることになる。私は、自分のわがままを通すことよりも、明るい性格の妻から笑顔を奪わないことのほうが家族にとっての幸福だと考えた。これが自宅での生活をあきらめて施設生活を続けることを選択した理由だ。
受傷当初は、妻や娘に何もしてやれない自分に生きがいを失い、顔がかゆくても自分でかけない不自由にいら立ち、体の苦痛に耐える毎日……いっそのこと、がんが見つかっても治療せずに死んでしまいたい、と考えていた。
電動車椅子を操縦できるようになって、娘が欲しがっていた犬を飼うと、近所の公園でドッグランに付き合えるようになった。
パソコン操作ができるようになって、娘にパソコンの使い方を教えたり、携帯電話に音楽や動画を取り込んでやったりした。
家族の役に立ったり、一緒に楽しい時間を過ごせるようになると、「死んでしまいたい」という気持ちが薄れていったように思える。いつの間にか「受容」の過程を経たのか否かは、未だに自分自身では正直言ってわからない。最近でも頻繁にギターを弾く夢を見るような私にとっての「受容」とはどういうことなのか……
2年前に受傷後で初の消化器内科のがん検診を受けて、食道がんが見つかった。早期がんだったので、内視鏡的粘膜下層剝離(はくり)術(ESD)により摘出手術に成功した。受傷から2年後に生命保険会社2社へ保険金請求して受給時に解約となったが、がん保険は契約を継続していた。手術から半年後の術後経過観察で無事と診断されたあとに、がん保険会社へ申請書を送った。数日後、その保険会社から「がん保険とは別に重度障害補償の保険にも加入しています」という連絡が入った。私にはそんな契約をした記憶はなかったが、がん保険の申請書に添付した診断書に“頸髄損傷”と書いてあるのを見て教えてくれたのだ。なんと親切な保険会社だろう!と驚いた。一時給付金に加えて、生存期間中は月額給付金が継続するという契約内容で、しかも受傷時まで遡って支給してくれた。テレビCMに出てくるアヒルがかわいく見えるようになった。妻と娘から「ガンバって長生きしてねー」と愛情のこもった励ましの言葉をもらった(笑)。今後は1ヶ月でも長く生きることで家族の役に立てる。がん検診を考えた時点で「死にたい」ではなく「少しでも長く生きなきゃ」と考えるようになっていた。
受傷時に5歳だった娘が、今年の春、世界初の脊髄損傷再生治療に成功して脚光を浴びているS医科大学の医学部を受験した。合格し、入学した \(*^o^*)/。2次入学試験の面接で「父が頸髄損傷なので、この大学で研究開発している脊髄損傷再生治療にとても興味があり、できれば自分もその研究開発に携わっていきたい」と志望理由を話したとのことだった。ちょうど報道発表の直後というタイミングもあり、面接官のウケがとても良かったらしい。ここでもひとつ娘の役に立てたということになるのかなぁ……(笑)
孫というのはかなり可愛いという話をよく聞くので、孫の顔を見てからあの世に行って、もしも生まれ変わることができるなら、超かわいいペット犬になって孫と遊びたいなどと夢を見ている。🐕
編集担当:戸羽 吉則
全員参加企画
いいモノ見つけた! ~32~
【OPOLAR充電式首掛け扇風機】


昨年からこの扇風機を室内や外出でも利用しています。
首にかけても軽くテーブルに置いても利用でき、充電式なので風力が強く長時間利用できます。
価格も安いので頸損には使ってみる価値あり。
価 格:アマゾン(ネット通販)で1,799円くらい
紹介者:M.I.
 『臥龍窟日乗』-60-歴史学と歴史小説
『臥龍窟日乗』-60-歴史学と歴史小説 
ある特定の人物を評価するとき、Aさんは「立派な人だよ」と言っているのに、Bさんが「いやいやケツの穴の小さい奴だ」とちゃちゃを入れる話はよくある。
Aさんが正しいのか、Bさんが正しいのか、われわれは判断に窮する。Bさんの評価は、過去にその人物と金銭トラブルでもあって、腹いせなのかもしれない。あるいは両方とも当たっている場合だってありうる。ことほどさように人物評価というのは難しい。
これは人物評価にとどまらない。事件の真相にしても、証言者の立場によって全体像は異なってくる。被害者の身内が証言者だと、どうしても加害状況におおげさな尾鰭(おひれ)が付く。
百田尚樹さんの『日本国紀』や井沢元彦さんの『逆説の日本史』など、いちれんの歴史本に、歴史学者呉座勇一(ござゆういち)さんが朝日新聞紙上で嚙(か)みついた。
「歴史ノンフィクション」は、史料に基づかない想像を多く交えており、学問的な批判に堪えるものではないと。そしてこれらの本を『俗流歴史本』と斬りすてた。
井沢さんが『週刊ポスト』で反論した。歴史家のほうこそ、重箱の隅をほじくるがごとく史料一辺倒で、作家の想像力こそが核心を捉えることもありうると。
歴史学の世界では、史料の信憑性(しんぴょうせい)を一次史料、二次史料と区分けしている。呉座さんによると「一次史料というのは、事件を見聞した当事者が事件発生とほぼ同時に作成した史料のこと」だそうだ。
信長が、浄土宗門徒と法華宗門徒にさせた論争を安土宗論(あづちしゅうろん)というが、これを八百長とする歴史学会に、井沢さんは反論する。その論拠として『信長公記』やルイスフロイスの『日本史』をあげた。これに対して呉座さんは『信長公記』もルイスフロイスも二次史料であると退けた。
はたしてそうだろうか? ちょっと冒頭に戻っていただきたい。ものごとは見る角度によって、また見る人の立場によって変わってくるものだ。「事件を見聞した当事者が事件発生とほぼ同時に作成した史料」のみ、信憑性があると決めつけてしまってよいものかどうか。
若いころ筆者は歴史をかじったことがある。将来、小説をやろうと目論んでいたからだ。だが歴史が好きというのと歴史学をやるというのは、根本的に違うのだと思い知らされた。
歴史学とは、それこそ重箱の隅をつつくように資料を読み込み、矛盾がないか検証する緻密な作業だ。とても根気が要る。こりゃオレにゃむかんわと尻込みしたものだ。
ここで思い出したことがある。
司馬遼太郎さんが『龍馬がゆく』をはじめとする歴史小説を書いていたとき、「司馬史観」は史実にあらずと非難の声が出た。司馬さんは「司馬史観」などというものは存在しないとうそぶいた。
司馬さんはけっこう丹念に史料にあたられる方だが、いちいち史実を追っていたら『龍馬がゆく』はじつにつまらない物語になったことだろう。
坂本龍馬は司馬さんによって維新の英雄になったが、歴史学者の目でみると、商社の腕のいい営業マンという位置づけと相成る。
大政奉還は龍馬の発案ではない。すなわち請け売りは得意だが独創性がない。教科書から削除すべきだとの議論も出たくらいだ。
だが世間は、いつの時代も英雄伝説を望んでいて、それはそれでいいのではないか、と筆者は考える。
井沢さんと呉座さんの論争を見ていて、そもそも歴史学と歴史小説は根本的に異なるものだと痛感する。昨今の歴史ブームを俎上(そじょう)にあげて、呉座さんが目くじら立てるのも分からぬではない。
ちょっと調べてみると井沢さんは、今年一月に亡くなった梅原猛先生を尊敬しておられるというが、呉座さんは梅原先生が創設された国際日本文化研究センターの助教だそうだ。
外科医と内科医が喧嘩をおっぱじめたが、ともに同じ大学の出身者であったというようなものだ。どうも筆者には兄弟喧嘩のように思えてならない。
蛇足ではあるが、梅原先生は筆者の教養課程の師でもあった。あの温厚な先生が、あの世で「もうおよしなさいよ」と眉をしかめておられるように思えるのだ。
千葉県:出口 臥龍
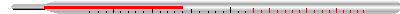
【編集後記】
今年も低気圧や前線の停滞により豪雨被害が多発しましたが、読者の皆様は無事に過ごされていらっしゃるでしょうか? ここ数年の異常気象の原因として諸説あり、フロンガスによる北極圏のオゾン層破壊説、二酸化炭素を主とする温室効果ガスの濃度増加説、そもそも地球の長い歴史の中で周期的に繰り返されてきた気象変動説など、いずれにしても人類にとって未知の領域……怖いですよね! 😫
さて、ネット版のリンク集を10数年ぶりに更新しておりましたところ、リンク先のURL変更など、行方不明のサイトは思い切って削除しました。新たにお勧めのサイトがございましたらメールでお知らせください。
次号の編集担当は、瀬出井弘美さんです。
編集担当:戸羽 吉則
………………《編集担当》………………
◇ 瀬出井 弘美 (神奈川県)
◇ 藤田 忠 (福岡県)
◇ 戸羽 吉則 (北海道)
………………《広報担当》………………
◇ 土田 浩敬 (兵庫県)

 post_card_comm_14520@yahoo.co.jp
post_card_comm_14520@yahoo.co.jp
発行:九州障害者定期刊行物協会
〒812-0054 福岡市東区馬出2-2-18
TEL:092-753-9722 FAX:092-753-9723
E-mail:qsk@plum.ocn.ne.jp

![]()
 ホームページ
ホームページ
 ご意見ご要望
ご意見ご要望