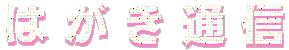 |
No.157 2016.2.25. Page. 1 . 2 . 3 . 4 . |
『夜と霧(新版)』書評 −5− (つづき) ●群衆の中にまぎれこむ 《強制収容所の人間は、みずから抵抗して自尊心をふるいたたせないかぎり、自分はまだ主体性をもった存在なのだということを忘れてしまう。内面の自由と独自の価値をそなえた精神的な存在であるという自覚などは論外だ。人は自分を群衆のごく一部としか受けとめず、「わたし」という存在は群れの存在のレベルにまで落ちこむ。》というのも羊の群れのような被収容者は常にサディスティックな犬どもに殴りつけられるから、おびえて群れのまんなかにもぐりこもうとする。《強制収容所に入れられた人間が集団の中に「消え」ようとするのは、周囲の雰囲気に影響されるからだけでなく、さまざまな状況で保身をはかろうとするからだ。被収容者はほどなく意識しなくても五列横隊の真ん中に「消える」ようになるが、「群衆の中に」まぎれこむ、つまり、決して目立たない、どんなささいなことでも親衛隊員(ss)の注意をひかないことは、必死の思いでなされることであって、これこそは収容所で身を守るための要諦(ようてい)だった。》 車椅子は群衆の中にまぎれこめない。どうしたって目立ってしまう。中途障害者はそれがいやで家に閉じこもりがちになる。最近でこそヘルパーに車椅子を押されて町なかを行く老人がふえたが、わたしがひとりで外出する決心を固めた1980年代の終わりには、外で車椅子を見かけることはほとんどなかった。なぜひとりで出かけたか(出かけるといっても半径1.5キロメートル程度のことだが)。詳しくは次の節で述べたい。 《苦しみをともにする仲間と四六時中群れて、日常のこまごまとしたことを常にすべて共有していると、この耐えざる強制的な集団からほんのいっときでいいから逃れたいという、あらがいがたい衝動がわきおこることは、よく知られた事実だ。ひとりになって思いにふけりたいという、心からの渇望、ささやかな孤独に包まれたいという渇望がわきおこるのだ。》アウシュビッツからガス室のないバイエルン地方の病囚収容所に移送され、ようやく医師として働けるようになると、人間らしい欲望が頭をもたげてくる。さいわい病棟の裏手に死体を放り込んでおく仮設テントがあった。《バイエルンの田舎の広びろとした花咲く緑の牧草地や、青くかすむ遠い丘陵をながめたものだ。そして憧れを追い、愛する妻がいるとおぼしい北や東北の方向に思いを馳せるのだが、そこには不気味なかたちの雲が認められるだけだった。》 美しいバイエルンの風景とともに描かれる妻への憧憬のあとに、なぜ《不気味なかたちの雲が認められるだけだった。》という不吉な文章を付け加えたのかわかるだろうか。解放後この本を書いたとき、妻がすでに死んでいることを知っていたからだ。その暗示として書いているのだ。このてはわたしも処女作でつかったが、詳細には触れまい。自慢話と受けとられかねないから。 ●自立と孤独 このひとりになりたいという気持ちは、全介助の身体障害者にはよくわかる。頸損歌人の故中島虎彦氏の短歌にもこの心が詠われていた。「すみませんありがとうの日暮らしにすこし疲れて野道までくる」という歌だ。わたしも散歩に行くときはいつもひとりだ。初対面のひとはそれを聞くといつも驚く。危険なこともある。不便なこともある。しかし全介助で常にそばに介助者がいなければ生きていけないからこそ、たまにはひとりの時間を過ごしたいのだ。 そしてもう一つひとりで出かける理由がある。連綿とつづいた「措置」の時代、すなわち障害者を弱者として行政がすべてを決定するという時代から、2005年、「障害者自立支援法」という法律が成立し、障害者が主体性を持って日常生活および社会生活を送れるようにするという時代に変わった。とたんに世間の流れが反転した。障害者は主体性を持って自立しなければならぬ! 社会参加しなければならぬ! できれば納税者になること! そこで従順な小市民であるわたしは、介助用車椅子をボランティアに押してもらい床屋へ行っていたのを、ヘッドレストの取れる電動車椅子を新調し、ひとりで床屋へ行くようにした。またたとえばひとりでスタバに入った。これはじつに勇気のいることだった。夏、阿佐ヶ谷駅近辺まで出かけるとのどが渇くし暑くてたまらない。自動販売機はそこら中にあるが、ひとりでは飲めない。車椅子の背後につけたリュックに水筒を入れ、そこから伸ばしたシリコンチューブを口元にセットするという方法もあるが、気が進まなかった。 スタバの前を行きつ戻りつし、「ま、いいや、今度にしよう」と帰ったことが何度あったことか。混んだ店の中に大きな電動車椅子で入っていって、もしいやな顔をされたらどうしようとおそれたのだ。仏頂面のケアほど心の冷えるものはない。ある日おもいきって入るとかわいい女の子が愛想良く出迎えてくれ、アイスコーヒーを飲ませてくれた。ストローでチュルチュルと一気に飲んでそそくさと店を出たが、この日の体験は大きな自信となった。これぞ自立ではないか。これぞフランクルのいう《主体性をもった存在》の証ではないか。 ところがだ。これまで個別の介護事業所としか交渉してこなかったのが、65歳になって介護保険の適用者になったとたん、ある日わが家で「全体会議」というものが開かれて、ケアマネ数人、各介護事業所の責任者、ヘルパーなどが集まり、全部で10人ぐらい来宅しただろうか、その場で「要介護度5でひとりの外出はまかりならん」と申し渡された。自立支援法の時代は良かったではないかと反論したが、その時代もほんとうはダメだったのだといわれた。それでは「自立」支援の精神に反するのではないか。勇をふるってスタバに入ったり、ひとりでスーパーマーケットなどの店に行き、ほかの客にかごを膝の上にのせてもらったり、品物をかごに入れてもらったり、レジでウエストポーチの中に財布が入っているからそこから金を取ってくれと頼んだりして、みんなに親切にされた行動は、あっけなく否定され、終焉を迎えた。あとはヘルパーに車椅子を押されて外出するヨボヨボなじじいになる日を待つしかない。これぞ国の思い描く介護保険の姿なのだ。そんな政治思想で「毎年老人介護費が1兆円ずつ増えていくから消費税を上げる」などと甘ったれた愚痴をこぼすんじゃねえよ。 「立ってる者は親でも使え」ならぬ「誰でも使え」という考えの深層には——これはすでに拙著に書いたことだが——、国立リハビリテーションセンター病院の精神科医師のことばがある。つぎの診察日を決めるとき、わたしが「その日はリハビリがあるから……」とためらうと、「みなさんリハビリの意味を誤解している。リハビリというのはあなたがいま乗っているストレッチャーのままデパートにひとりで置き去りにされたとき、自力で無事に自宅に帰り着くことです」といわれた。そのときは意味がわからなかったが、これこそフランクルのいう「主体性」を如実にあらわした言葉なのだということにいまさらながら気づく。 (つづく・次回、最終回) 東京都:藤川 景
私は9年前に膀胱ろうの手術を受けましたが、4ヶ月ぐらい前から、膀胱ろうの穴のふちに潰瘍ができるようになりました。 潰瘍ができるのは、カテーテルが膀胱ろうの穴のふちを圧迫していることが原因だというのが泌尿器科医師の見解で、処置はイソジン消毒ジェル塗布が適当だと言われました。しかし、その処置をして、カテーテルの圧迫を和らげる目的でガーゼ保護をしても、治りかけては、また悪化の繰り返しでした。 皮膚科の医師に診察してもらったところ、いきなり液体窒素スプレーを吹き付けられ、処置はイソジン+キズ薬混合ジェルという処方でした。その後、1週間で潰瘍は治りましたが、数日後、再発してしまいました。 その後、同じ場所に生キズが絶えない状態が続いたため、このままではまずいと思い、自分で対策を考えなければならないと意識し始め、潰瘍の原因となっているカテーテルの圧迫を防ぐための小道具を自作することにしました。 まずは手始めに、発泡スチロールを材料にして、断面が凹型で3cm四方・1cm厚のブロックを作成し、穴のそばにカテーテルを乗せてテープでとめて数日間様子を見ました。カテーテルが穴のふちに接触しないため、潰瘍が治りかけているのが確認できました。第1弾で成功かと思いきや、副作用として、ブロックが当たっている部分の皮膚が赤くなってただれているのが見つかり、失敗となりました。発泡スチロールの硬さと通気性の悪さが駄目だったのだと考えました。 次に、低反発ウレタンフォームでブロックを作成し、前回と同様に穴のそばにとめて様子を見ることにしました。今度は、材質が軟らかすぎるようで、うまくいきませんでした。 現在、通販サイトで見つけた硬さが数種類セットになったウレタンフォームを購入し、その中で中ぐらいの硬さのウレタンフォームでブロックを作成して様子を見ています。 「はがき通信」誌面版およびインターネット版の読者の中には膀胱ろうの手術を受けた方が大勢いらっしゃると思います。私のように潰瘍ができて、その対策をされている方に、その実践概要をご教示いただけますよう、ぜひともお願いいたします。 編集担当:戸羽 吉則 ◆ ヒトiPS細胞由来のオリゴデンドロサイト前駆細胞を損傷脊髄に移植し再髄鞘化に成功 −脊椎損傷に対する さらなる機能回復につながる発見− 慶應義塾大学医学部生理学教室(岡野栄之教授)と同整形外科学教室(中村雅也教授)は、ヒトiPS細胞から効率的にオリゴデンドロサイト前駆細胞へと分化誘導する方法を開発し、マウス損傷脊髄の再髄鞘化に成功しました。 脊髄損傷に対する神経幹細胞移植による機能回復メカニズムの一つとして、移植細胞の再髄鞘化が重要であることが知られています。髄鞘は、神経細胞から伸びる軸索を覆うことで絶縁シートのように働き、脊髄内の非常に速い神経伝達を可能にしています。しかし、ヒトiPS細胞由来神経幹細胞は主にニューロンに分化し、髄鞘の形成を担うオリゴデンドロサイトへの分化が進みにくいという課題がありました。 脊髄損傷に対するヒトiPS細胞由来神経幹細胞移植の臨床応用が、近い将来に実現されようとしています。従来の細胞移植でも有意な運動機能の回復を認めていましたが、この成果によって、さらなる機能回復を望める可能性が示唆されました。 (2016年1月18日 慶應義塾大学医学部 プレスリリース 抜粋) Webサイト URL: http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2015/osa3qr000001bw2h-att/20160118_01.pdf ◆ ヒトiPS細胞由来の神経幹細胞の凍結保存法を確立 −脊髄損傷に対するiPS細胞由来神経幹細胞移植の臨床応用に向けて一歩前進− 慶應義塾大学医学部生理学教室(岡野栄之教授)と同整形外科学教室(中村雅也教授)は、株式会社アビー、日本ユニシス株式会社との共同研究により、ヒトiPS細胞由来の神経幹細胞の安全かつ効率的な凍結保存技術を開発し、従来の緩慢凍結法と比較し、凍結融解後の細胞生存率を向上させることに成功しました。 患者さん自身の細胞からiPS細胞を樹立し、現行の培養法で神経幹細胞へ誘導して移植する自家移植では、脊髄損傷に対する最適な細胞移植時期に細胞の生成が間に合いません。そこで本研究チームは、京都大学iPS細胞研究所のiPS細胞バンク構想に基づいた他家移植を計画しています。これを実現するためには、iPS細胞バンクから譲渡を受けたiPS細胞を神経幹細胞へ誘導し、凍結保存しておく必要があり、細胞生存率の高い保存方法が求められていました。 (2016年1月25日 慶應義塾大学医学部 プレスリリース 抜粋) Webサイト URL: http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2015/osa3qr000001c244-att/20160125_01.pdf ◇ お詫び 156号「呼吸ペースメーカーを埋め込む」のなかで「呼吸ペースメーカー」の翻訳記事の文章が重複していました。お詫び申し上げます。なおネット版では訂正されております。 【編集後記】
この冬は、当初は暖冬という長期予報で、各地で桜などの木々が狂い咲きするほどの暖かさが続いていましたが、1月下旬になって、全国的な寒波の襲来による記録的な積雪量や低気温といった異常気象になり、皆様、寒さ対策に大変なご苦労をされたことと思います。お疲れ様でした。 今年が皆様にとって良い1年になりますよう、お祈りいたします。 次号の編集担当は、藤田忠さんです。 編集担当:戸羽 吉則
<呼吸ペースメーカーの補足説明> 肺に空気を吸い込む時は、胸と腹の境にある横隔膜を下の方に下げ、胸の中の圧力を低くする必要がある。そこで、横隔神経に適当な間隔で電気刺激を与えて、横隔膜を動かそう、というのがこのペースメーカー。体の外にある大きなマッチ箱ぐらいの刺激発生装置から出された高周波は、胸の表面にとりつけたアンテナを通じ、皮下に埋め込んだ受信機に伝えられる。ここで高周波は電気信号に変えられ、首のあたりに埋め込んだ電極を通して横隔神経を刺激する。 (1980年4月4日 朝日新聞 抜粋) ………………《編集担当》……………… (2015年2月時点での連絡先です) 発行:九州障害者定期刊行物協会 |
![]()
| ホームページ | ご意見ご要望 |