

 マスコミから
マスコミから 
 脊髄損傷の治療にiPS由来の細胞を移植
脊髄損傷の治療にiPS由来の細胞を移植
世界初 慶応大など発表 
慶応大学などのグループは、脊髄を損傷して手や足が動かせなくなった患者に、iPS細胞から作った神経のもとになる細胞を移植する臨床研究の、世界で初めての手術を実施したと発表しました。
これは、慶応大学医学部の岡野栄之教授と中村雅也教授らのグループが14日、オンラインで会見を開いて発表しました。
グループは、事故などで脊髄を損傷して体が動かせなくなったり感覚がなくなったりした患者に、iPS細胞を使って神経を再生する研究を進めてきました。
今回、グループは、脊髄を損傷して4週間以内の患者に対して、iPS細胞から作った神経のもとになる細胞を200万個移植する手術を行ったということです。
脊髄損傷の患者にiPS細胞から作った細胞を移植する手術は、世界で初めてだということです。
グループによりますと、手術後の経過は順調で、1年間にわたって安全性に問題がないかなどを慎重に確認していくということで、今後さらに3人に手術を行って安全性や有効性を確認する計画だということです。
脊髄損傷は国内では毎年およそ5000人が新たに患者になるとされていて、根本的な治療法はなく、治療法の開発が待ち望まれています。
会見で慶応大学の中村教授は「大きな一歩であることは間違いないが、新たな一歩でもある。2例目、3例目と続けて、臨床に届けていきたい」と話していました。
また、岡野教授は「ここに来るまで長い時間がかかったので、1例目の手術を実施できてうれしく思っている。今後、脊髄を損傷してから時間がたった慢性期の患者への応用も含めて研究を続けたい」と話していました。
◇脊髄損傷とは
脊髄損傷は、背骨の中にある脳と全身をつなぐ神経が傷ついて、体が動かなくなったり、感覚が失われたりする症状がでます。
国内では10万人以上の患者がいるとされ、毎年、およそ5000人が交通事故などで新たに脊髄損傷になっているとみられています。
神経の損傷の場所や程度により、動かなくなる場所や症状の重さが異なっていて、中には自分で呼吸することも難しく、人工呼吸器が必要な人もいるということです。
脊髄のような中枢神経は、一度傷つくと自然には再生せず、根本的な治療法も無いため、治療はリハビリなどが中心で、神経を再生させる再生医療の実現が待ち望まれています。
◇患者団体「ずっと待っていた」
脊髄損傷の患者や家族でつくる「日本せきずい基金」の理事長で、自身もスポーツの試合で脊髄を損傷して、肩から下をほとんど動かすことができないという大濱眞さんは「1例目の手術が行われることを、私たちはずっと待っていた。まずは安全性の確認が目標だと思うが、有効性も証明されることを願っている。手が動くようになるとか、自発呼吸ができるようになるというだけで、生活環境が大きく変わるので、早くそういった段階まで進めてほしい。脊髄損傷は、交通事故などで、ある日突然起きるもので家族もパニックになる。それが少しでもよくなれば、希望を持てるようになると思っている。今回は、けがをして間もない人が対象だが、慢性期の患者も対象になるよう研究が進むことを期待している」と話していました。
◇高齢化で転倒による患者の増加懸念
脊髄損傷の原因は、転倒と交通事故が半分以上を占めているとされ、高齢化が進むにつれて、転倒による患者が増えるのではないかと懸念されています。
日本脊髄障害医学会のグループは、2018年に脊髄損傷の救急患者を受け入れる全国の医療機関を対象に調査を行いました。
それによりますと、脊髄損傷の原因は、
▽平らな場所での転倒が38.6%
▽転落が23.9%
▽交通事故が20.1%だったということです。
1990年ごろに行われた同様の調査では、
▽交通事故は43.7%
▽転落が28.9%
▽平らな場所での転倒が12.9%だったということで、
およそ30年間で、転倒の割合が大きく増えているということです。
グループによりますと、転倒の割合が増えた背景には、高齢化により、高齢者が増えたことが影響している可能性があるということで、転倒による脊髄損傷は、今後もさらに増えるおそれがあるとしています。
(情報提供:令和4年1月14日 NHK)
 高齢者の電動車いす、踏切事故多発
高齢者の電動車いす、踏切事故多発
安全対策が課題に 
電動車いすに乗った高齢者の踏切事故が相次いだ。2021年8月から12月までに3件の事故があり、2人が死亡した。運転免許証の返上で電動車いすが便利な移動手段として利用する高齢者が増加していることも一因のようで、安全対策が課題になっている。
昨年12月9日に大阪府東大阪市の近鉄奈良線で、69歳の男性が普通電車と衝突して死亡。8月には香川県観音寺市のJR予讃線で75歳の女性が特急列車にはねられて亡くなったほか、11月には宮崎県門川町のJR日豊線で踏切内に立ち往生した80代の女性が、あわやのところで救出されるという事故も起きている。
独立行政法人「製品評価技術基盤機構(NITE)」によると、電動車いすに乗った高齢者の踏切内での事故は11~20年度の10年間に、兵庫や愛知、福岡、山梨県などで13件発生。60~90代の9人が亡くなっている。タイヤが線路の溝にはまったり、バッテリーが切れて線路内に立ち往生、列車と衝突した事例も報告されている。
電動車いすはバッテリーやモーターを積んでおり、手動式の車いすに比べて重い。その重量を支えるため、タイヤの幅が手動式に比べて太く、線路の隙間にはまると、なかなか抜け出せない。
総務省が21年9月現在として発表した65歳以上の高齢者は推計3640万人で過去最多を更新している。高齢ドライバーによる死亡事故が相次いだこともあり、運転免許証を返上する高齢者が増えている。
免許を返上した高齢者に電動車いす購入の補助金を出す自治体もある。岐阜県大野町は自主返納者支援事業として購入費の一部助成(上限5万円)を、鳥取県大山町は上限10万円で購入費の二分の一を補助している。
電動車いす安全普及協会(静岡県浜松市)によると、20年度の出荷台数は約1万9400台。協会担当者は「利用は高齢者が多い。買い物や通院に自転車や徒歩ではつらいという人や、加齢により足腰が衰えてきた高齢の人が主に使っている」と話す。
電動車いすはこれまでの福祉機器から高齢者の移動手段として、役割が大きく変わってきた。NITEの担当者は「介助者がいない場合や夜間の踏切横断は避けてほしい」と呼び掛けるが、地元自治体や警察署が中心になって、電動車いすの利用に関する講習会を定期的に開催するなど、安全対策の必要性が高まっていきそうだ。
(情報提供:令和4年4月10日 福祉新聞)
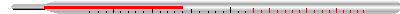
【編集後記】
今号では、編集担当を就任してからはじめて(無償化に伴い)原稿依頼ゼロで編集させていただきました。
そして誌面の関係で「『はがき通信』を次世代にバトンタッチするためのお願い」を掲載していませんが、引き続き一縷(いちる)の希望を託して募集しております。どんなことでもゼロから立ち上げていくのは大変なことだと思います。四肢マヒ者の情報交換の形が動いている内に、どなたかにバトンタッチできますように、まずは懸念事項のお問い合わせなどお待ち申し上げております。
*
次号の編集担当は、瀬出井弘美さんです。
編集担当:藤田 忠
………………《編集担当》………………
◇ 瀬出井 弘美 (神奈川県)
◇ 藤田 忠 (福岡県)
………………《広報担当》………………
◇ 土田 浩敬 (兵庫県)

 post_card_comm_14520@yahoo.co.jp
post_card_comm_14520@yahoo.co.jp
発行:九州障害者定期刊行物協会
〒812-0044 福岡市博多区千代4-29-24 三原第3ビル3F
TEL:092-753-9722 FAX:092-753-9723
E-mail:qsk@plum.ocn.ne.jp

![]()
 ホームページ
ホームページ
 ご意見ご要望
ご意見ご要望