| は が き 通 信 | Number.27−P2 | |
| POST CARD CORRESPONDENCE | 1994.5.25 |
|
リハビリテーション工学カンファレンスと私
KU▲有名人だからでしようか?お手紙を頂いて、書こうか、書くまいか迷ったのですが、前々からリハエカンファレンスに参加していて感じ、思ってきたことと一部通じるようなところがある気がして、思い切って書いてみました。 もちろん社交辞令のようなものとは思っていますが、私の何処をとって有名人って言葉が出て来るのでしょうか? 私達障害をもって、日々の生活で、自分の生きる道を模索し右往左往している者にとって、うまく言えませんが、はたして有名人って、有名になるって、自分の心の中に、気持ちの中にある目標のような、満足感、達成感のようなものを満たさずしてあり得るものなのでしょうか? あるとしたら、それはどんな物で、どんな意義と価値があるのでしょうか? スミマセン!?暇にまかせて理屈をこいて・・・・・ 今日書こうとしたことはそんなことではなくて・・・・・
今回お手紙にありました研究所を始め、他の研究機関でも、もし実際にそう感じられるような事があったとしたら、それは私が、イヤ!わたしに限らず、有名、無名とは関係ないところに原因があると思いますし、Gさんに「有名人になりなさい」と言われるよりも、是非これから私の書くようなことに気をつけ、心がけてもらった下さい!?
▲研究機関との係わり 私は、リハエ学協会に入れていただいて、カンファレンスに参加するようになって早9年目、確かに、ある時期カンファレンスに参加されるメンバーの中にも、例えば受傷直後より何かとご指導を頂いている先生との関係を始め、他の研究所の先生との関わりについて、個人に肩入れしすぎだとか、おまえは得している!とか、様々なことを言う人もあり、私も悩みましたし、私に関わりを持っていただいた先生方も大変な悩まれたようでした。
でも、最近では、大変生意気を言うようですが、テクニカルエイドの必要性が叫ばれ、見直されるようになるにつれ、そうした見方や意見もなくなり、むしろ現場との関わりをいかに持つか?障害者の声をいかに拾い、とらまえるか?という観点から、参考にし、見直そうとする中で、好意的なものに変わっているようにさえ感じています。
つまり、これからの私たち障害者の生活を支えてくれる福祉機器、特にその機器の開発にあたって、私たち障害者も、従来からの消極的な姿勢、あるものを黙って使う、使わせてもらう的発想から、少しでも機会をとらまえて、少しでも自分たちの使いやすいものにしていくために意見を、発言に機会をつくっていく!そんな当事者としての関わりをもっていかなくてはならないはずで、そう考えたとき、これまではあまりにも声を発する障害者がいなかったことも事実です。
そんな中で、たまたまラツキーなことに、こうしたことに多少人よりは興味もあり、ほんの少しの知識もあったことと、側に声をかけ、かけられ相談できる機関があり、これはまさしくラツキーの一言なのですが、私は四肢の機能を全く失い、途方にくれ、自分でできることなら何でも、たとえ器械のカを借りてでも・・・と思い求めたし、研究者側は、言葉は悪いが少しでも重度の研究対象(幅広く応用が効くため)を求めていたしで、まさに磁石が引き合うかのような出会いのあったことも事実ですが、その当時、私が最初に訪ねた研究者を訪ねていたのは私でけではなく、また、他の人たちが一度もしくは数度で足を運ばなくなった中、そう考えると、持前の厚かましさがあったことがうまく噛み合う元だったのかも知れませんが・・・。
とにかく、このことは最近私のところに沢山の方から相談があり、よく研究所を紹介したり、中には橋渡しまでしてあげるにも関わらず、実際に問い合わせをする人がいないことでもわかるように、困ったり、悩んでいる障害者はいるけど、自分でそれが解決するまで努力する根気のある障害者があまりにも少ないことも事実です。 それに、これは私が一番気をつけ、心がけていることですが、そうしたお願いをする際に、研究所や機関に頼めば何でも、すぐに作ってもらえる!と思い込んだり、自分で何も努力しないで、ただの便利屋かなにかのように頼みっぱなし、利用しっぱなしの姿勢は良くないと思います。
最近感じるのですが、こうした機関を利用?してる人は結構います。でも、悲しいかな利用し、自分の願いが叶うと後は知らん顔、そればかりか、最近では、利用したいだけ利用しておいて(例えば、こうした機関の本来の仕事、取り組みと違う、スイッチの付け変えひとつのようなことにも頻繁に研究者を呼びつけ、振り回した位にしておいて・・・)ある程度身の回りの目度が付いたら、そこで得た知識やノウハウをサッサと利用して、それを商売にしたり、そればかりか商売のために利用しようとする障害者まででてきており、とても憂慮すべきことも事実としてあります。
▲福祉機器の開発で心がけていること 私がものを頼むに当って、確かにリハカンに第1回から参加し、そこで築き上げた人間関係があることは事実で、否定したら嘘になると思います。それがなかったら、今のようなスムースさもなかったかも知れません・・・。 でもこれは胸を張って言えることですが、端から見られてどう映っているか知りませんが、私だって最初から、何でも作ってもらうために、全ての相談や漠然とした状態を含めて、無節操に話しを持ち込んでいるわけではありません!
まず、自分の中に何か困ったり、ニーズがでてきたら、自分なりにじっくり考え、案を練り、必要な情報収集をし、検討した上でまず(1)自分でやれる範囲、女房もしくは身内で解決することと、(2)身のまわりの知人でやってもらえること、(3)業者や専門ボランティア(たまたま大阪の自助具の部屋に昔からの知り合いがいて)で頼める範囲・・・と、自分なりのランクを分けて解決に当っています。そして、どうしてもそこの中で出来ないことや、トータル的な知識、総合的な技術力のいるような事や、新規の開発に当るようなことのみを依頼するように心がけています。
その場合も、まずこちらの内容に応じて、各機関の最初の取り組みの資料に目を通し、何処にお願いするのが一番最適かを考え、決め、その上で単にこんなものが作って欲しい!だけではなくて、出来る限りグローバルな立場に立ってものを考えるようにし、公益性を見つめ、必要なデーターやアンケートも場合によっては取って添付したり、自分のニーズをわかりやすく伝えるために、図画や原理図、回路的なことも簡単に書いたりしてお願いするように心がけています。
今回の電動車イスも、今継続中の複数のテーマもそうした経過をたどり、特に車イスに関しては、前回も書きましたが、たまたま補装具研で新回路が開発されているところで、こうした持ち込み方が成功し、お願いした日に、この考え面白いかもしれないね!?一度試して見るか!?ということになり、試したところOK!で、取り組みが進行したようなわけです。
(これはすこし余談になりますが、車イスに関してでも、出来るまでの1年ほどは、ほぼ毎月のように東京に日帰り(=懐が寒くて)ですが、通いました。 ここら当りの時間的なことや経済的問題、介護者のことや本人の体調、体力などなど、私達が一つの物を人に伝え、作ってもらうにはとても多くの問題点も抱えています) ▲フイードバックの重要性 また、今回もリハカン初め、機会を捕まえて、同じように困っている人を初めとして出来る限り情報提供をしていこうと思っていますが、私たちが研究所にお願いしたとき心がけないといけないことの一つに、こうした情報提供と、開発していただいた物に対する正しい評価、意見のフイードバック、反映も決して忘れてはならないことだと思います。 そうした取り組みが、少しずつ、一つづつ、本当に私たちのためになる器械を生み出すことにつながるのではないでしょうか?
私は、こうした関わりを待たせてもらう中で、いつも、自分の生活環境に新たなものを加え、便利にしていただいた先生に対し、感激の気持ちと同時に「次に先生にお会いするまでに、これを使って少しは成長を!」「そのときまでに、何か新しい自分の可能性に挑戦を・・・」と心がけるようにしています。
私が、これまで10年近く、下手で恥をかきながらもリハカンに参加し、あれこれと場を濁させてもらってきたのもここにあって、もうそろそろ私のようなオジンは退散しなくては・・・と思うのですが、なかなか同じような思いで参加し、後に続いてくれる人がいなくて、ついつい続けていますが、本当に障害者のために物作りということを考えたら、これではいけないし、ここらあたりに今の日本の障害者の悪い面、消極的な面があるようで、それゆえに私のようなものの存在が、今回のご指摘のようになって来るのかも知れませんし、現実に研究機関から可愛がって?もらっていることにつながる?のかも知れませんが・・・少し寂しい気もしますネ!? だから、私のようなものがシャシャリでて、あちらこちらの研究所を荒し、良いわけはありませんが、今少しの間、やむおえず続けていこうと思っています・・・。 ▲これからのこと なんだか書いている自分が解らなくなってきましたが、福祉機器開発への!関わり、研究機関との関わりにおいての私の思いが少しでも解っていただければ幸いです。 最後になりましたが、Gさんのためにカナダの車イスのことを問い合わせてみえるようですが、私も向こうの呼気庄式の車イスは実際に試させてもらってきましたが、日本の電動に対する基準(最高6km)や、給付制度のことを考えるとなかなか導入も難しいのでは?と考えます。 ちなみに、今回使われている新回路は、呼気庄にも対応できますし、センサーの数も幅広く対応可能です。何か応用が効くはずです。Gさんにも使えるような機会が生まれましたら、どんなに素晴らしいことか願っています!
1994年2月
広報部だより
広報部長・麩澤孝▲施設生活の近況 やっと、暖かくなってきましたね。私も日中は、電動車イスで外に出ています。 これから梅雨までの期間が、私達にとって一番よい季節です。思いきり日光浴しましょう。4月下句で、施役生活も2年が過ぎました。今まで、褥瘡の跡がむけたり、治ったりするくらいで、これといった大きなトラブルもなく過ごしてきました。
入所当時「はがき通信」を始め、色々な障害者団体の機関誌にカーサ・ミナノでの生活の様子を書いてきました。当時と較べ今は、ケア・ワーカー(寮母・寮父)の数も毎年土増えて、今では基準以上の数まで達しています。最近では、日中・深夜もほとんどナースコールも鳴らなくなり、職員も入居者の生活のパターンがわかり、介助を頼む前に、来てくれるようになっています。しかしその反面では、決まった時間以外での介助や、突然のナースコールなどは、あまり気持ちよくやってもらえるとは言えません。外出についても、本人・付き添い共に誓約書を書かされたり、門限の矩縮など、そういったことが入居者の知らないところで決められてしまったことも事実です。
施設入所以前、施設で生活しながらも、在宅生活をされている皆さんのように暮らして行くのが、私の希望でしたが、希望がかなえられているとは言えません。 最近では、施設なのだからしかたないのかぁ…なんて思っている今日この頃です。 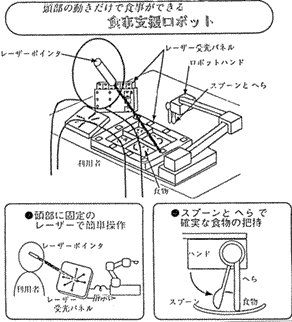 ▲食事介助支援ロボット ▲食事介助支援ロボット国立身体障害者リハビリテーションセンターの研究所の研究員2名と、セコム社開発員2名が、3月中旬にカーサ・ミナノへ見えられ、食事介助支援ロボットを使い始めて食事をしてみました。 まず、本体をテーブルに乗せるのですが、座面の高い電動車イスでは、足がテーブルの下にはいらず苦労しました。 食べ物をスプーンですくい、口まで運ぶ動作はロボットがしてくれますが、食べ物をうまくつかむ位置にスプーン持って行くのに、頭に付けたレーザーポインタでの指示に時間がかかり、食事が終わるまでは、だいぶ時間がかかるようです。 これから、レーザーポインタの受光部を大きくしたり、少しでもすくいやすいようにスプーンを大きくする予定です。
このロボットはあくまでも支援であり、テーブルの位置やレーザーポインタのセッティング、それに最後まできれいに食べるには、数回食べ物をすくいやすい場所へ寄せる必要があり、やはり人間の介助が必要です。
このように、リフターなど人間を直接介助する機器には、それぞれいろいろな考えがあり「人間に気を使いながらしてもらうなら機械の方がいい」という人もいれば「やはり人間が人間を介助するのが本来だ」という人もいる。ある身体障害者療護施設では、施設長の考えでリフターや特別浴など使わず、入居者全員が職員に抱いて浴槽に入れてもらう所まであるそうです。私自身の考えでは、介助猿や介肋犬は別として、介助者の軽減を考えればある程度、福祉機器にたよるのは仕方のないことだと思います。皆さん、ロボットに食事介助してもらうなんて抵抗ありませんか? この食事介助支援ロボットの開発は、随時「はがき通信」で報告していきたいと思います。
1994年5月5日
海外情報・その7
HK受傷のタイプ、レベル、完全か不全かということと反応する率には関係がなかった。精子の量は正常であったが、精子の運動性や形態に異常の見られるものがかなりあった。精子が異常になる原因として前立腺液の出ない人や、高い熱で睾丸を冒された人、再発する尿道炎、抗生物質などの薬によるものなどが考えられた。副作用は6%の人に見られた。
パイプレータをペニスに当てることにより反射で射精することができる。この刺激は簡単で安全で、傷つけることもなく、痛みもない。そして医師にたよることもなく、家庭でできるという利点がある。この方法でうまくいかない人には、経直腸的電気刺激(transrectal
electrostimulation)という方法もある。
パイプレータの振動数は60〜120ヘルツ、振幅は1.5〜4.5ミリ、最大刺激時間は1〜5分(3〜5サイクル)で当てた。 428人の脊損者がこの方法を試みたが、その年齢は16歳〜45歳で、受傷後、18年から39年経っていた。 副作用では高位脊損者では自律神経反射障害がみられた。他にとくに射精中や射精後に頭痛や血圧の上昇などの自律神経反射障害がみられた。他には腹筋の痛みを伴う収縮や、亀頭部のすり傷や出血や表面の潰瘍(かいよう)がおこった。
何人かの脊損者では数回の挑戦で初めて射精した人もいる。さらに最初に成功した人で、そのあとは射精がおこらなくなった人もいた。
これが成功するかどうかのめやすで重要な要素は、足の裏を引っかいた時にヒップ反射があるかどうかということである。これがある人は75%の成功率で、無い人は0%の成功率であった。この反射はL2(腰髄)とS2(仙髄)の間に損傷のある人には起こらない。同時に海綿部と肛門部の反射がない人は成功しがたい。頚髄と胸髄の損傷者は成功率が高く、91%にもおよぶという報告もある。これは射精に必要な下位の脊髄が冒されていないためと思われる。
T5(胸髄)以下の脊損者ではこの精子を集める試みは家庭でしても安全であるし、T5レベルより上の人でも自律神経の機能障害は薬で防ぐことができるので、副作用を心配することはない。
射精した精子の質については、今十分な資料がないが、大体において精子の量は2cc以上で正常なものが多いが、その形態や運動性についてはかなり異常が見られる。 ある報告によれば、この試みを何回も続けた方が後の精子の濃度と運動性は良くなるが、精子の形態は悪くなるという結果がえられた。 また受傷後6ヶ月以内の精子は運動性が悪いため十分な授精能力をもっていず、その上、受傷後6ヶ月以上経った人の方が精子の質も運動性も良いという研究報告もある。
たとえ精液が量的に、そして質的に十分なものでなくても、これは人工授精や試験管ベビーや顕微鏡での受精など、いろいろなテクノロジーを駆使することによって利用できるものである。さらに最も妊娠させ易い精子を選ぶ技術も進みつつあるので、妊娠する可能性はますます増えてくる。
将来的には、神経生理学的なメカニズムを理解し、精液を得る可能性や精液の質にかんしていろいろな刺激の特徴に関する基礎的な研究が必要である。基礎研究に加えて臨床的な試みも行って、脊損者の射精できない人に最適な治療法をみつけることが必要である。 これは国際バラプレジア医学会の機関誌「バラプレジア」に掲載されたオランダの研究者の文献を抄訳したものである。 「The effectiveness of vibratory stimulation in anejaculatory men With spinal cord injury. Review article,H Beckerman Msc PT,J Bech6r MD,G J Lankhorst MD,Paraplegia Vol.31,PP.689ー699」
あとがき
*神奈川のKさんたちの機関誌「F・L・C」は郵送費節約のため第三種郵便の許可を取りました。その申請部数を満たすため、通信の名簿をお貸ししました。みなさんの手元にも「飛璃夢」が届いていることでしょう。編集の西川さんから、はがき通信も同じような主旨だから合併してはと提案もいただいています。 今回も皆さんから切手のカンパをいただいていますが、はがき通信はすでに手作りの限界に来ています。いますぐではありません。これからの通信についてみなさんのご意見をおよせ下さい。 *海外情報は今回で7回目となりました。毎回、Kさんは頚損の人たちがどんな情報を必要としているか、という視点で紹介する文献・資料を選択して下さっています。医学の進歩は激しく、専門情報は洪水のように抑し寄せてきます。専門用語の訳だけでもたいへんなのに、電話連絡などすべて無料奉仕で引き受けてくださっています。 ワープロはつかわず、電話で情報をよせて下さる方が何人かいます。今回代筆で通信を寄せてくださったHIさんもその一人でした。KFさんと相談して今回から電話通信の欄をもうけました。ワープロを使っていない方、どうぞご利用下さい。 *入力ミスやコピーミスには十分配慮しているつもりですが、毎回何ケ所かあるようです。申し訳ございません。
電話通信 KF氏よりアンケートのお願い 今のA4版の通信は自分の装置に合わない、ほかの人はどうやって読んでいるのだろうとF氏から電話で問い合わせがありました。そこでつぎのようなアンケートを用意しました。次号の通信までにぜひ回答して下さるようお願いします! 1四肢マヒの方に伺います。はがき通信をどんな方法で読んでいますか。 ① 介助者にもってもらい、ページをめくってもらって読む ② ベッド上で読み板(できれば写真かイラストで)にはさんで一人で読む ③ 車椅子で読み板(できれば写真かイラストで)にはさんで一人で読む ④ その他、工夫したもの(できれば写真かイラストで)を使って読む ⑤ 人に読んでもらっている ⑥ 家族が読んでいる ⑦ その他( ) 2 通信の紙面の大きさについて注文はありますか。 ①今のサイズ(A4)では大きい、B5が良い ②今のサイズ(A4)で良い ③今のサイズ(A4)では小さい、B4が良い ④その他(具体的に) なお、KF氏の暮らしぶりは、主婦の友(1994年5月号)に「アイ・ロング・フォー・イエスタディ」というタイトルで写真入りで紹介されています。短いスペースに本質をとてもよく掴んだ内容で、まじめな取材に好感を持って読ませていただきました。 |