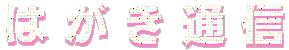 |
No.124 2010.8.25. Page. 1 . 2 . 3 . 4 . |
「はがき通信」のみなさま 3月の沖縄懇親会では、大変お世話になりました。「ミントの会」のパシャイさん、大澤さん夫妻と一緒に参加させていただき、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。初めて行った沖縄で、忘れられない思い出ができました。ありがとうございました。 さて、ゴールデンウィークにパシャイさんと大澤さんとイランに行ってきました。今回のイラン渡航では、パシャイさんの実家があるキャラジというテヘラン近郊の小都市に滞在し、パシャイさんがこれまで支援をしてきた何人かの方のご自宅を訪問させていただきました。 イランでお会いした方々に関しては、パシャイさんと大澤さんのNPO法人「ミントの会」からご紹介させていただければと存じます。ご興味のある方は、「ミントの会」のホームページをご覧ください。 http://www.geocities.jp/mint_assist/report.html イランは、欧米諸国や日本に比較するとまだ十分ではありませんが、中東では常に福祉先進国として頑張ってきた国です。障害者支援のための法や制度を整備する努力もされてきました。しかし、多くの場合在宅で暮らしている障害者の生活実態を考えると、まだまだ問題がたくさんあります。 一つは経済的な問題です。現在、イランでは国家福祉局という機関が障害者の支援をおこなっています。たとえば、ベッドや車イスの給付や貸与、生活費の支給などのプログラムです。しかし、たとえば生活費として国家福祉局から支給されるのは、1ヶ月3500円くらいで、これは一月分の薬を購入したら終わってしまう金額です。 イランには健康保険や年金もあります。また、生命保険や自動車保険もあります。しかし、その保障は部分的で、自動車事故で重篤な後遺症をもつような状況になった場合であっても、保険金がもらえないということがあります。非正規の被雇用者であったら、年金ももらえません。このような時は、その後の生活費に困ることになります。現在のイランでこうした人たちを支えているのは、親戚や地域の人たち、モスクなどの宗教施設がもつ基金、あるいは民間のNGOや個人の慈善家などです。 もう一つは、リハビリも含めた身体管理の問題です。イランでは入院期間が非常に短く、十分なリハビリを受けることなく退院になります。医師・看護師から退院後の生活に関する指導はほとんどありません。本人も家族も、障害について、体調管理の方法や介護法について、何も知らないまま自宅での生活をはじめなければなりません。 受傷後、退院後の生活指導やリハビリの指導がない状態では、自宅での生活環境を整えるのでさえ一苦労です。こうした問題への対処には、障害や随伴症状、合併症などに関する知識の提供と具体的な生活状況に対応した指導(相談)が必要です。毎月の生活費を援助するような経済的支援は大きな予算がなければできない活動ですが、基本的な知識の提供、生活の指導や個人の相談にのる活動なら、小さな団体でも少ない予算でもおこなうことができます。 パシャイさんはこれまで、日本から送った車イスやベッド、クッションなどの福祉機器を脊損者の方々に提供するのと同時に、同じ障害をもつ仲間として、いろいろな悩みや相談にのってきました。そして、今回、そうした方々のお宅にうかがってみて、家庭環境や身体状況に合わせた生活の方法に関して相談できる人がいるというだけで、彼らの生活が大きく変化することがわかりました。何でも話せる仲間がいるということは、とても大切なことです。その時々にはいろいろな問題があっても、仲間との交流があれば孤独に悩むことは少なくなります。以前に比べて表情が明るくなった訪問先の皆さんのお顔を見て私も本当に嬉しくなりましたし、勇気が出ました。 「ミントの会」の活動は、一人ひとりの自宅を訪ねていくという、非常に地味で地道な活動です。しかし、当事者のパシャイさんだからこそ、できることがたくさんあります。今回のイラン渡航では、その活動が確実に成果を出している様子を見ることができました。そして、その活動を支えてくださっているのが、日本の当事者の方々です。「はがき通信」の皆さまとの出会いも、とても大きな力になっています。本当にありがとうございます。 今後、もっと直接的に日本とイランの交流ができたらと考えています。そのために、「ミントの会」と協力しながら、私ができることを少しずつ準備していこうと思います。翻訳等、進まないことも多くご迷惑をおかけいたしておりますが、また、いろいろな機会におじゃまさせていただけたらと存じます。皆さまからご意見やアドバイスを頂戴できましたら幸いです。これからも、どうぞよろしくお願いします。 東邦大学医学部看護学科 細谷 [これまでの人工呼吸] けい損で横隔神経マヒレベルと診断されれば、大半は安定した人工呼吸のため、気管切開による侵襲的陽圧換気の人工呼吸となる。横隔神経マヒレベルでは主な呼吸筋、横隔膜を動かせず、自力呼吸困難と診断される。そのため自力呼吸訓練なく24時間人工呼吸依存となり、気管切開から必要な空気量を確実に肺に送り込むため、太めのカフ付きカニューレが使用される。その結果、気管切開孔から上にある声帯に空気が通らず、声が出せなくなる。人工呼吸器は生命維持装置であり、生命維持に必要な空気量を確実に肺に送り込むことが最優先される。 その対処は人工呼吸管理の先進国、カナダ・バンクーバの医療でも同じ、ただし、バンクーバでは受傷直後の危機状態から脱し症状が安定後、人工呼吸器の離脱困難と診断されれば、退院後の地域生活を目標として声帯に空気が通るようカフ付きからカフなしの細めのカニューレに切り替え、話す訓練を開始、座位と電動車イス使用の訓練も始まる。呼吸器の機種も在宅用に切り替え、長期の座位姿勢に対応できるよう呼吸回路も気管切開孔に負担がかからない材質と組み立てが工夫される これまで日本のけい損人工呼吸療法では、この切り替えが実施されてこなかった。長期人工呼吸依存と診断されても、退院後の社会生活より生命維持が優先されてきた。話すことよりも生命維持に必要な空気量を確実に肺に送り込むことが優先され、話すことは犠牲にされてきた。 これまでに気管切開せずにけい損者に導入された人工呼吸はNPPV以外にもあった。たとえば横隔膜ペーサやニューモベルトである。ただし、横隔膜ペーサはマヒした横隔神経の代わりに体内に埋め込んだペーサで横隔膜を動かす“侵襲的な”人工呼吸である。日本でも数人のけい損者が導入しているが、保険が適用されず高額な自己負担が必要、かつ長期使用による筋疲労の問題もあり、普及には限界があった。 ニューモベルトは、米国で呼吸リハビリテーションを受けたバンクーバの故ワンさんが使用していた。バンクーバでニューモベルトを使用していたのはワンさんだけだった。これはコルセットのようなベルトを腹部に装着し、陽圧人工呼吸器でベルト内に空気を送り込む人工呼吸である。“非侵襲的”だが、座位姿勢でのみ使用可能な人工呼吸であり、ワンさんもベッド上では通常の気管切開による人工呼吸を使用していた。バンクーバに行くたびにワンさんを訪問したが、いつもニューモベルトは快適との回答だった。しかし、バンクーバの専門家はその長期使用に否定的であった。腹部への長期圧力の副作用を案じていた。その後、ワンさんは奇跡的に自力呼吸が可能になり、ニューモベルトが不要になった。しかし、数年後、突然、肺炎のため亡くなった。 今、考えると、ワンさんはNPPVの適用者だった。彼は夜間のみ人工呼吸だったので、気管切開は閉じ夜間のみNPPVで対応できた。ワンさん以外にも夜間のみ人工呼吸が必要なけい損者もいた。この人は受傷後しばらく24時間人工呼吸だったが、訓練によって日中自力呼吸が可能になっていた。この人も気管切開のままだった。日本のけい損者に比べ吸引は非常に少ないので、専門家に夜間のみの人工呼吸なら気管切開は閉じてもよいのでは、なぜ閉じないのかと聞いたことがある。答えは、彼のように長いことTPPV—気管切開による侵襲的陽圧換気療法でいると、NPPVへの切り替えには抵抗が強く、本人が希望しないとのことだった。バンクーバでも最近のけい損者はICUの段階でNPPV導入が多いそうだが、人工呼吸歴の長い人たちがNPPVに切り替えたという例は聞いていない。 バンクーバには気管切開による人工呼吸器使用40年以上の人もいる。その人に気管切開ケアについて尋ねると、もう生活の一部、慣れてしまったし、気管切開孔も自然の孔、肛門のような存在とのことだった。この人も日中は電動車イスで過ごし、呼吸回路は日本の人たちのような硬さではなく、柔軟なゴム製の回路なのでそのうえから上着を着用でき、スカーフで気管切開孔を被い、正面からは人工呼吸器使用には見えず、ハイセンスでおしゃれを楽しんでいた。 バンクーバのように、地域呼吸管理システムによって人工呼吸器使用者に対するサポート体制が充実していると、気管切開の有無は日本の当事者のように深刻な問題ではないようにみえる。 [NPPVがこれからの人工呼吸になるには] Hさんが10年間のTPPV後、NPPVに切り替えた直接の要因は気管切開孔が徐々に拡大、人工呼吸器から送風される空気の漏れが大きくなり、気管切開を閉じる必要に迫られてのことだという。しかし日本のけい損者の多くはそのような障害なしでも気管切開の閉鎖を考える。幼稚園が気管切開では受け入れ拒否のため、あるいは気管切開による医療ケアからの解放を願って。 気管切開を伴うこれまでの人工呼吸と同様の効果が期待できるのがNPPVと、その導入促進者は主張する。しかも気管切開による医療ケアが不要となり、さらに深呼吸をし、声帯を閉じて息溜めができ、肺や胸郭の稼働性を維持、呼吸リハビリテーションになるという。だがその導入と普及には当事者が安心してそのメリットを享受できる体制整備が必要であり、実際に取り組む医師の増加や呼吸ケアスキルの開発向上がこれからの人工呼吸には不可欠と考える。 編集顧問:松井 和子 |
![]()
| ホームページ | ご意見ご要望 |